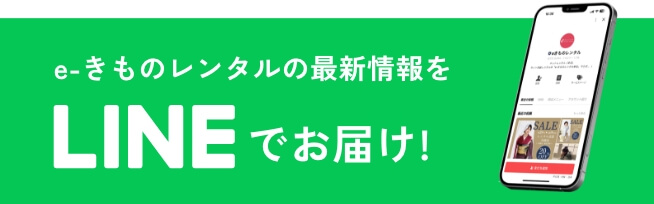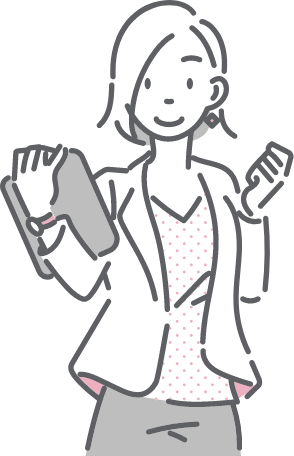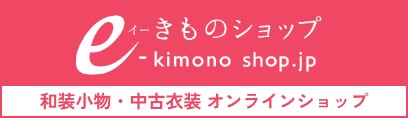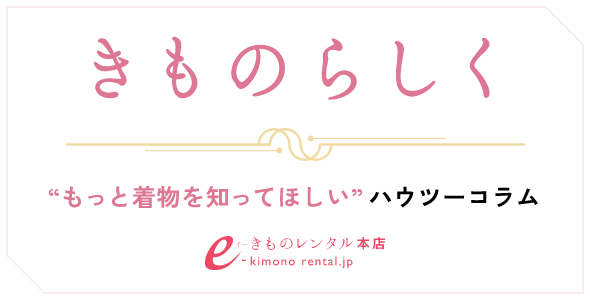
【七五三】靴の選び方:草履やブーツ・革靴など和装・洋装別おすすめ&年齢別のポイント・靴擦れ防止対策も解説

【七五三】靴の選び方:草履やブーツ・革靴など和装・洋装別おすすめ&年齢別のポイント・靴擦れ防止対策も解説
七五三のお参りや写真撮影でお子様の足元を飾る靴選び。どうしても衣装にばかり目が行きがちですが、七五三の靴では注意すべき大事なポイントがありますし、履物をどのようなものにするかでコーデ全体のイメージが意外と左右されるため、軽視できません。
そこで本記事では、和装・洋装に合わせた選び方、男の子と女の子のそれぞれの年齢に合った靴選びのポイントを特集します。おすすめの靴擦れ対策や当日持っておくと便利なアイテムについてもご紹介するので、これからお子様が七五三を迎える親御様は、ぜひ参考にしてください。
七五三の日程や年齢は?

七五三は、3歳の男女、5歳の男の子、7歳の女の子の健やかな成長を祝う行事です。パパやママをはじめご家族にとっては、お子様の成長を実感できる楽しみの一つとも言えるでしょう。
それぞれの年齢で意味合いが異なり、3歳は髪を伸ばし始める「髪置(かみおき)」、5歳ははじめて袴を着る「袴着(はかまぎ)」、7歳は大人と同じ着物を着る「帯解(おびとき)」に由来します。
3歳の「髪置」は、それまで剃っていた髪を伸ばし始める儀式で、子どもの健やかな成長を願う意味があります。5歳の「袴着」は、男の子がはじめて袴を着用する儀式で、社会の一員として認められることを意味します。7歳の「帯解」は、女の子がそれまで着ていた紐付きの着物から、帯を結ぶ着物に変える儀式で、大人の仲間入りを意味します。
三・五・七というのはいずれも奇数ですが、中国で偶数よりも奇数の方が縁起がいいとされ、その考え方を取り入れ、男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の時期(昔は数え年でしたが、今は満年齢が一般的)に神社やお寺に参拝し、健やかな成長を神様にお願いしてご祈祷を受けます。
七五三のそもそもの起源は、平安時代にまで遡ると言われています。当時は乳幼児の死亡率が高く、子どもが無事に成長することは決して当たり前ではなく、大変喜ばしいことでした。そこで、子どもの成長の節目に、氏神様にお参りして今後の健康を祈るようになったのです。生後すぐに赤ちゃんの時に行うお宮参りに比べて、確実に大きくなったお子様の成長をお祝いし、感謝する意味も込められています。
七五三の時期は、11月15日前後とされていますが、大変混み合うため、時期をずらして行っても構いません。
早ければ8〜9月頃から受け付けている神社やお寺も多いですし、12月中旬くらいまでならまったく問題ありません(これ以降は七五三のご祈祷を受け付けてもらえないケースが多いので注意しましょう)。
お子様にも七五三の意味を話してあげよう
上記のように七五三には大変重要な意味が込められています。しかし、最近では親たちすらその意味をよく理解しないまま、伝統的な行事だから行うのが当たり前として形式的に済ましてしまうケースが多いかもしれません。でもそれでは、本当の七五三の意味をなしませんし、少し勿体無いと思いませんか?
七五三の主役はお子様です。
「生まれてきてくれてありがとう!」
「七五三、おめでとう!」
「これからも〇〇ちゃんが元気で過ごせるように神様がお力をくれるから、みんなでお祈りに行きましょう」
「大事な神様に会いにいくために、綺麗な服を着ていきましょうね」
「いい子でいられたら、これからも嬉しいことがいっぱいあるよ」
「ご褒美に美味しい千歳飴がもらえるからね」
というように、お子様が理解できるようなポジティブな言葉がけや説明をして、お子様自身に自覚を持たせてあげるのはいかがでしょうか。きっと、不機嫌になったり、ぐずったりする確率はグンと下がるはずです。
せっかくの神聖な行事が、後味の悪いものにならないように、もし不機嫌になっても一方的に叱らず、「今日はいい子で頑張ったね」「ありがとうね」と労をねぎらったり、感謝の言葉をかけてあげたりすることも忘れないようにしましょう。
七五三の靴選びでもっとも大事なこと

七五三の靴を選ぶうえでもっとも大切なポイントは、見た目のデザインやおしゃれさ、かっこよさでしょうか?というと答えは、NO。
一番大事なのは、「安全性」です。とくに3歳のお子様は、自分で歩いたり走ったりできるといっても、まだ足元がおぼつきませんので、せっかくの行事で転んでは大変です。5歳や7歳でも、慣れない靴を長時間にわたって履き続ければ靴擦れをおこして痛い思いをさせることにもなりかねません。
お宮参りの時は赤ちゃんでしたから、お参りする神社やお寺に足を踏み入れるのも、ほぼ初めてと言ってよいでしょう。すると、目新しい光景に興奮が抑えられず、大人が考えもしない行動に出ることがあります。その起点となるのは、100%足からです。
そのため、石や木の根っこ、階段等、思いもしない場所でつまずいたり、他の参拝者と接触したりといったトラブルには十分に注意しなければなりません。こうしたことを想定して、そのお子様にとってもっとも履きやすく、快適で、素材も軽量といった安全性の高い靴を選択する必要があるでしょう。
さらに、靴擦れを起こさないための対策や、普段とは不慣れな靴が少しでも履きやすくなる工夫にも気を配りたいところです。その辺りについても、後ほど詳しく解説していくので、ぜひチェックしてください。
七五三の靴:和装と洋装でどう選ぶ?
七五三用の靴は、大きく和装用と洋装用の2種類に分かれます。和服にするか洋服を着るかによって、当然、履物も違ってきます。
和装は、シンプルに表現すると「着物」のこと。
3歳の男の子は、着物に「被布(ひふ)」というベスト状のアイテムをセットにして用いるのが一般的です。5歳の場合は、羽織に袴というスタイルが人気です。
3歳の女の子は男の子と同じく、着物に被布がオーソドックスなスタイルです。7歳では、大人になって結婚式や卒業のイベント等で着用するのと同じような着物に、帯を締めます。
こうした和装に合わせるのは、草履が基本ですが、七五三では安全性を考慮して履きやすくて歩きやすいサンダルやブーツ、足袋型のスニーカー等も用いられます。
一方、洋服は、男の子なら、タキシード等のフォーマルウェアやスーツ、女の子は、かわいいドレスが一般的です。これらに合うのは、革靴が基本ですが、履き心地や見た目のおしゃれさを考えてスニーカーやカジュアルシューズ、ブーツを選ぶ方も珍しくありません。
和装に合わせる靴:草履・サンダル・ブーツ・足袋型スニーカー

七五三の和装には、伝統的な草履が用いられます。
草履の構造は、「台(だい)」と「鼻緒(はなお)」からなります。台は足を乗せる、靴で言うと靴底にあたる部分で、鼻緒は、足を固定するために台に3点で固定された紐を指します。鼻緒を台に挿し込んでいる部分を「前坪(まえつぼ)」と呼びます。
草履を履く際は、靴下がわりに足袋を履きますが、その足袋が接触する台の表面を「天(てん)」、裏面(地面との接触面)を「底(そこ)」と呼びます。草履の側面を見ると何層かに重なっていることが多いですが、ここを「巻き(まき)」といいます。
ちなみに、草履の中でも「雪駄(せった)」と呼ばれる種類がありますが、雪駄は一般的に男の子向けの履物として利用されることが多いです。畳表になっており、草履に比べると平たく薄いのが特徴です。
草履や雪駄のサイズの目安は、以下の通りです。
3歳・・・16〜16.5cm
5歳・・・18cm
7歳・・・21cm
参考までですが、木製の台でできたタイプを「下駄(げた)」といいます。下駄は男性も女性も履きますが、大人向けが基本のため七五三で使用されることはありません。
ただ、小さなお子様にとって草履は歩きにくく、慣れない履物で長時間を過ごすのは大きな負担になることもあります。そのため、最近では足袋型スニーカーやサンダル、着物にも合うおしゃれなショートブーツ等を選ぶ方も増えています。
足袋型スニーカーは、聞き慣れない方も多いかもしれません。その名の通り、着物で靴下代わりに履く足袋のように、親指とその他の4本の指部分にセパレートになっているスニーカーのことで、最近ではその種類もずいぶん増えてきました。
大工さんや建設業の職人さんが建設現場で履いているイメージがありますが、足にフィットして柔軟性があり、防水性があるものやカラーバリエーションも豊富でファッション性に優れたものもあるので、チェックしておく価値はありますよ。
冒頭でもお伝えしたように歩きやすさや安全性を最優先に考え、お子様が快適に過ごせる靴を選ぶことが何より大切です。
そのため、伝統的なスタイルである草履は魅力がありますが、お子様の年齢や体力などを総合的に考慮して、サンダルやブーツなどの選択肢も検討してみましょう。
足袋を選ぶ際には、素材に注目します。綿やベロアなど、吸湿性、通気に優れた柔らかい素材を選ぶことで、お子様の足を快適に保てます。
洋装に合わせる靴:フォーマルシューズからスニーカーまで

七五三で洋装を選ぶ場合、靴の選択肢はぐっと広がります。
女の子なら、可愛らしいストラップシューズやリボン、レース、フェイクファー等の飾りが付いたデザイン性の高いパンプスが人気です。
男の子は、フォーマルな印象のローファーをはじめとする革靴(実際は価格が安価でソフトな合皮で十分でしょう)がおすすめです。ただし、革靴は硬いため、お子様によっては嫌がるケースもあるでしょう。
その場合は無理強いせず、お子様の好みを重視して、動きやすく疲れにくいスニーカーにしても問題ありません。歩きやすくて足を守ってくれる低反発性のインソールが入ったものが、とくにおすすめです。
カラーは、女の子の場合、白やピンク、赤等の明るい色の靴が人気です。男の子は、黒や茶色、紺等の落ち着いた色がおすすめです。
年齢別に見る七五三の靴選び
七五三の靴選びは、年齢によって重視すべきポイントが異なります。3歳、5歳、7歳と、それぞれの年齢のお子様に最適な靴を選ぶために、各年齢ごとのポイントを詳しく見ていきましょう。
3歳の七五三:歩きやすさ最優先!
3歳のお子様は、まだまだ足の発達段階です。そのため、洋装で靴を選ぶ際には、何よりも歩きやすさを重視しましょう。転びにくく、安定感のあるフラットな靴を選ぶのがおすすめです。
また、自分で脱ぎ履きしやすいように、マジックテープ式のものを選ぶとよいでしょう。あるいは、甲にゴムベルトが付いているタイプもおすすめです。靴底もすべり止め加工がされていると安心ですし、素材も布やナイロンなどの柔らかくて足にフィットしやすい商品を選んであげてください。
着物の場合でも、転倒の恐れがあるため無理に草履や雪駄を履かせる必要はありません。お子様の負担にならないような靴を選んであげてください。とくに女の子の場合は、桜や梅などのかわいらしいお花などがあしらわれたデザインを探してあげるのもおすすめですよ。
ただ、草履や雪駄にする場合、3歳児は、16〜16.5cmが一般的です。
サイズは、お子様の足の長さを正確に測り、できるだけそれに合ったものを選ぶようにします。足の長さは、かかとから一番長い指先までの長さを測り、その長さに1cmほど余裕を持たせた草履や雪駄を選ぶのがおすすめです(通常、大人の場合は、足のサイズより小さめの草履を選びますが、お子様の場合はその限りではありません)。
5歳・7歳の七五三:おしゃれも意識して

5歳と7歳になると、しっかりと自分で歩けるようになるため、靴選びの選択肢もグンと広がります。
洋装の場合、女の子なら、少しヒールのあるパンプスやブーツ等、おしゃれを楽しめる靴を選んであげましょう。カラーは、ホワイトやレッド、ピンクなどが人気。ブーツは、ブラック、ブラウン、グレーなどが定番ですが、最近ではピンクやパープル系、ニュアンスカラーなどもランキングの上位を占めるようになりました。
男の子なら、ローファーやスポーティーなスニーカー等、大人っぽく、見映えもするかっこいいデザインがおすすめです。
ただし、長時間履いても疲れないよう、履き心地も考慮することが大切です。とくに女の子は、ヒールが高すぎたり、足に合わなかったりすると、靴擦れや転倒の原因にもなるので注意が必要です。
とはいえ、この年齢になると、お子様自身も自分の好みがはっきりしてきます。靴を選ぶ際には、お子様もお買い物に連れていくなどして、本人の意見を尊重し、一緒に選ぶのもよいでしょう。本人が好きな可愛いデザインや色の靴を選ぶことで、七五三がさらに楽しい思い出になるはずです。
和装の場合は、草履や雪駄の他に、女の子なら着物に合ったブーツもおすすめです。
女の子の草履のカラーは、ゴールドやシルバー、薄めのピンクなどが品と清潔感がありますし、どのような色や柄の着物にもマッチするのでおすすめです。エナメル性のブラックも、大人びた雰囲気が楽しめるのでよいかもしれません。
まったく柄がないタイプもスッキリしてよいですが、とくにガールズやキッズ用は、桜や梅、菊などの可愛いお花や蝶などがあしらわれた商品も多いので、できるだけ色々なデザインをみながらお子様に選ばせてあげるのもよいでしょう。
大人の場合も含めて、着物用の草履は、手にもつバッグや巾着のデザインと似たようなものやまったく同じものを履くことが多いです。そのため、着物や帯の柄や刺繍だけでなく、巾着やポシェットをもったときに見映えがするデザインかどうかも意識してチョイスしてあげましょう。
男の子の草履は、基本的にホワイトです。清潔感だけでなく、堂々とした男の子らしい風格も演出できますが、他にも、ブルーやブラウン、ベージュなどおしゃれなカラーもあるので、着物のデザインやお好みに応じて選んでみるのもよいでしょう。
雨が降ったらどうする?
雨が降った際、洋装は別としてとくに和装の場合は、草履だと滑りやすくて大変危険です。雨天用のビニール製草履カバーがありますが、ほとんどは大人用のため、お子様用は手に入りにくいかもしれません。よって、お参りする神社やお寺、写真スタジオまでは長靴にして、到着したら履き替えさせてあげるとよいでしょう。
必見!おすすめの靴擦れ対策

洋装で革靴の場合、履き慣れていないと靴擦れを起こす可能性が高いです。そのため、あらかじめ市販の靴擦れパッドをかかと部分にセットしておくとよいでしょう。シリコン等の小さなクッション材でできているので、摩擦を軽減できます。
一方、和装で草履を履く場合は、鼻緒が硬すぎたり、細すぎたりすると、足の指の間が痛くなり、長時間履くことができなくなります。とくに、初めて草履を履くお子様には、鼻緒が柔らかく、痛くなりにくい素材を選ぶことが重要です。
鼻緒の素材は、綿やベロア等がおすすめです。生地の肌触りが良く、柔らかいので、お子様の足にとてもフィットしやすくなるからです。また、鼻緒の幅も重要です。幅が広すぎると、足にフィットせず、歩きにくくなります。幅が狭すぎても、歩く際にバランスを崩しやすくなるため注意しましょう。
鼻緒の強さも大切です。鼻緒がある程度しっかりと固定されていないと、歩行中に鼻緒がずれて転倒の原因となる可能性があります。硬く感じても履く前に以下の方法で鼻緒を緩めれば問題ありません。左右一足ずつ行ってください。
- まず、草履のかかと部分を上に、つま先を手前にして、鼻緒の両サイドの付け根部分を親指と人差し指でつまみ、内側を外側に向かって裏返します。
- 次に、両手の親指と人差し指で挟むようにして、1で裏返した左右の鼻緒の付け根を持ち、それぞれを斜め上(右は右斜め上、左は左斜め上に)に押し広げます。
- 最後に前坪をつまんで上に向かって適度に引っ張ります。
こうすると鼻緒が緩んで履きやすくなりますよ。緩みすぎると元に戻せないため、最初は軽く緩め、お子様に履かせて様子を見ながら調整するとよいでしょう。
さらに、かかと止めがあると草履が脱げにくいうえに、転倒防止にもなるため、とくに3歳のお子様には必須のアイテムです。
かかと止めは、ゴムでできたベルトのような形状のタイプが主流で、鼻緒の左右の付け根にボタンでとめて、かかとにストッパーのように当てて使います。とくに脱ぎにくくなることもありません。草履に付属されていない場合は、数百円程度でキッズタイプが販売されているので、購入しておくとよいでしょう。
必ず着付けと歩く練習を

七五三の前に、必ず着付けと歩く練習を行うようにしましょう。
とくに和装の場合、本番当日の朝に初めて着させるのは、非常に危険です。お子様の中には着物を嫌がるケースがあるうえ、親御様も上手にきちんと着付けられない恐れがあるからです。
七五三の着付けは、お宮参りのベビータイプや浴衣などシンプルな着物とは異なるので、事前の練習は必須です。衣装を購入する場合は、お店の方が丁寧に着付け手順を教えてくれるでしょう。着物レンタルの場合も、親切なショップは「着せ方マニュアル」をプレゼントしてくれます。
それらを参考にして、必ず自分たちだけで着付けられるか確かめ、難しい点があっても本番までにクリアしておきましょう。七五三の当日は、朝から髪をセットしたり、親御様も着付けなければならなかったりして、結構バタバタします。着付けにかかる時間を事前に把握できれば、当日のスケジュールも立てやすくなりますよ。
ちなみに、七五三では、普通の着物以外に縁起物など関連の小物もセットで着付けなければならないため、その正しい付け方もチェックしておく必要があります。
参考までに、各年齢ごとに必要なアイテムを一覧でご紹介しましょう。
年齢 | 準備するもの |
3歳 | 着物 髪飾り 被布 長襦袢 足袋 草履(ブーツ)・巾着(ポシェット) 腰紐 |
5歳 | 着物 羽織 袴 長襦袢 お守り 袴帯(角帯) 足袋 草履(ブーツ) 腰紐 |
7歳 | 着物 髪飾り 長襦袢 帯揚げ 帯 帯締め しごき 筥迫(はこせこ) 末広(せんす) 足袋 草履(ブーツ)・巾着(ポシェット) 腰紐 伊達締め |
また、洋装でも和装でも本番で履く革靴や草履を、実際にお子様に履かせて歩く練習も行いましょう。
革靴は、しばらく歩くと違和感を覚えるポイントがだいたい分かるはずです。痛い部分があれば、そこにクッション材を入れるとか、絆創膏を貼ってあげるとよいでしょう。
草履は、先ほどご説明したように鼻緒を緩めると歩きやすくなりますが、それでも馴染むまでには時間がかかります。そのため、理想は何日かに渡り、1日に数分でいいので歩くようにすると、本番でより履きやすくなるでしょう。
とくに7歳の女の子については、着物姿が美しく映えるように、いつもより短い歩幅で、ゆっくりと内股で歩くように指導してあげるとよいでしょう。お母様が着物を着用する場合は、一緒に練習するのもおすすめです。
当日持っておくと便利なグッズ
七五三当日に持っておくと安心なグッズがいくつかあるので、ご紹介しましょう。
絆創膏
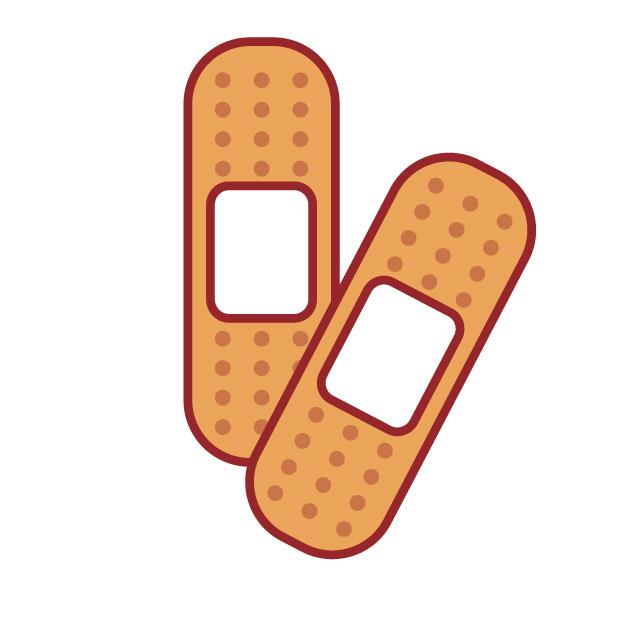
先ほどご紹介した対策をしていても、やむを得ず靴擦れを起こしてしまう可能性があります。そのような時のために、絆創膏を持参しておくとよいでしょう。左右の足の、親指と人差し指の間や、かかとなど複数箇所に貼らなければならないケースを想定して多めに用意しておきましょう。
履き慣れたシューズや靴下
とくに3歳や5歳のお子様の場合は、靴擦れを起こしたり、式が長引いたりすると、草履や革靴を脱ぎたがる恐れが十分にあり得ます。すぐに履き替えられるように、いつも使用しているシューズや靴下を持参しておくと安心です。
洗濯バサミ・着物クリップ
とくに着物の場合、トイレに付きそうのも一苦労です。裾や袴をたくし上げたまま無理して用を足すと、着物を汚してしまう恐れがあります。そこで、洗濯バサミや着物クリップを2つ以上もっておくと、裾などをそれらで留めて、わざわざ持っておく手間がなくなるので、とても助かるでしょう。
お気に入りのおもちゃ・おやつ・ペット
とくに3歳のお子様はイヤイヤ期の絶頂です。ちょっとしたことでも不機嫌になってしまう可能性が十分に考えられるため、気持ちをそらすための、お気に入りのおやつやドリンク、おもちゃなどもすぐに出せるようにしておくとよいでしょう。
また、七五三の記念に家族写真を撮影する際、写真スタジオによっては、特別にペット同伴が可能なケースがあります。お子様が大好きなペットがそばにいると機嫌よく過ごせることが多いので、無理でなければ連れていくのもよいかもしれません。
草履の入手方法

七五三用の草履を入手する方法には、購入とレンタルの2つのパターンがあります。それぞれのメリットについて解説しましょう。
購入する
レンタルは、好きなデザインというよりは決められた中からの選択肢になります。そのためお好みの色や柄の草履が履けるとは限りませんが、購入の場合は、お気に入りの商品を選べる可能性が高いです。きちんと手入れをして保管しておけば、弟様や妹様の七五三でも使い回しができるでしょう。
着物もセットで購入する場合は、お正月やお誕生日といった特別なイベントでも活用できるので、お得かもしれません。革靴やブーツは、ご入園やご入学、ご卒業でも使えるでしょう。
また、とくに呉服店などで着物もセットで購入する場合は、その道のプロがお客様に合う商品を勧めてくれたり、疑問点や使用後のケアの仕方などについて教えてくれたりもするので、安心でしょう。
着物レンタルを利用する
七五三の草履は、着物レンタルを利用すると無料で貸してもらえるので、とてもお得ですよ。七五三用の草履はメンテナンスや保管方法が少し面倒です。レンタルするとその手間が省けるメリットもあります。
滅多とありませんが、借りた草履の鼻緒が切れたりひどく汚れたりしても、替えの商品を貸してもらえるため安心です。
ちなみに、着物レンタルには、以下のようなメリットがあります。
- 豊富な商品の中から自由に選択できる(とくにネットレンタルならサイトで自由に検索して探せる)
- 人気のブランドや最新トレンドの着物が注文できる
- お子様だけでなく、他の家族の着物やスーツ、ワンピース等も安くレンタルできる(lineの公式アカウントから登録するとクーポンがもらえてお得といったサービスや・期間を限定したキャンペーン等が多い)
- 購入するより安い(オフシーズンならさらに格安でレンタルできるケースもある)
- ネットレンタルの場合はスマホがあれば、アカウント登録から申し込み、返却まで手軽に行える
- 商品を自宅に郵送で届けてもらえるため便利(送料無料のサービスも多い)
- 返却時も連絡をせずに送り返すだけ
- 急なニーズでも対応できる(ネットレンタルなら24時間・365日いつでも注文できる)
- 返却時のクリーニングが不要なため気軽に利用できる
- 着物だけの単品ではなく、小物(草履、長襦袢、腰紐、結び帯、帯締め、帯揚げ、伊達締め、バッグ、箱せこ、しごき、角帯、懐剣、羽織紐、末広(扇子)、お守り、足袋等)をセットで無料レンタル可能(お店によって内容は異なります)
とくにネットレンタルの場合、リアル店舗と違って試着ができないため不安という声がよく聞かれます。しかし、最近のショップでは専用サイトの商品ページで、鮮明な複数の画像とともにサイズについても細かく説明がなされています。
それに従って注文すれば、届いてからデザインが思った通りでないとか、サイズが合わないといったトラブルはほぼありませんので安心してください。
レンタルはショップによって価格、送料、サービス内容、営業時間等が異なります。詳細については、事前に各お店の案内に記載されている情報を参考にしたり、メールや電話で質問したりしておくことをおすすめします。
とくにネットショップの場合は、特定商取引法に基づく表記がなされているかのチェックも忘れないようにしましょう。
また、ひどく汚したり破損してしまったりした場合には、別途クリーニング代や補修代を請求されるケースもあります。そのような場合にそなえて賠償をしなくて済む1,000〜2,000円で加入できる安価な保険があります。気になる方は、問い合わせてみて、可能なら加入しておくと安心でしょう。
草履やシューズはいつまでに用意するの?

七五三は、11月15日ですから、多くの方はそれまでに草履や靴を用意すれば大丈夫とお考えかもしれません。しかし、そこに落とし穴があります。
家族で撮る記念写真を七五三当日に行うなら問題ないのですが、同じ日にお参りと撮影を済ますのは、スケジュール的に意外とタイトです。中には、祖父母様を呼んで食事会をするケースもあるでしょうから、これらをすべて1日の中に収めるのは、幼いお子様にも体力的に負担がかかるかもしれません。親御様もヘトヘトになる恐れがあります。
そのため、写真撮影を別の日に行う、「前撮り」や「後撮り」を選択するのもおすすめです。ただし、とくに前撮りの場合は、衣装はもちろん、草履や靴もかなり早い段階で手配しておかなければなりません。写真スタジオは、11月前後は大変混み合うため、少し早いと感じるかもしれませんが、8月〜9月に済ませてしまうやり方もあります。
購入にしてもレンタルにしても七五三関連の商品は、どうしても一時に集中して需要が高まるので、あまりに直前だと在庫が不足する可能性があるでしょう。そのため、衣装も草履や靴も、前撮りの数ヶ月前には探し始め、レンタルならお気に入りが見つかり次第、すぐに予約しておくのが無難です。
また、レンタルを利用される場合は、前撮り(または後撮り)と七五三当日の2回、衣装や草履などを借りる必要があるので、うっかりと忘れないように気をつけてくださいね。
草履のメンテナンスと保管方法
七五三用の草履は、履いた後のお手入れがとても大事です。保管方法にも気を配ると長持ちするので、ぜひ覚えておいてくださいね。
草履の正しいお手入れ方法
草履を履いた後は、以下の順でお手入れしましょう。
- 硬く絞った布で拭く:全体の汚れを落としますが、とくに底の部分は土や泥などで汚れているので、金蘭や刺繍を傷つけないように注意しながら入念に拭き取ります。水で流さないように注意。
- 底を上にして陰干しする:底を上に向けて直射日光の当たらない風通しの良いところで干します。4〜5日が目安。
草履の保管時の注意点
草履を保管する際は、通気性を重視しましょう。ビニール袋には入れず、草履を直接箱に入れて保管するのがおすすめです。お住まいの環境やスペース上、通気性に自信がない場合は、紙の箱に入れていくつか穴を開けておくとよいでしょう。折りを見て定期的に箱から出し、陰干しできるとなおOKですよ。
まとめ:七五三(753)の靴は安全でおしゃれなものを選ぼう

七五三の靴は、まず安全を最優先して選ぶことが大切です。和装なら草履、洋装は革靴と最初から決めつけず、お子様が長時間履いても負担にならないものを探してあげるのがおすすめです。その上で、選択肢があるようなら色や柄、形など、お子様が気にいるものにしてあげるとよいでしょう。
e-きものレンタルでは、七五三用の衣装を多数取り揃えております。3歳と5歳の男の子用、3歳と7歳の女の子用の人気のラインナップを幅広くご用意しております。
着物だけでなく、草履をはじめ被布、襦袢、腰ひも、お守り、しごき、末広、髪飾り、巾着(足袋はプレゼント!)といった着付けに必要な小物も、コーディネートのうえセットでお送りいたします。送料は日本全国無料(一部地域を除く)、ご返却の際はクリーニングも不要です。
兄弟や姉妹のスーツやドレス、ママの着物やワンピース、パパのスーツや羽織等が割安でレンタルいただける家族割引クーポンもありますので、ぜひご利用ください。