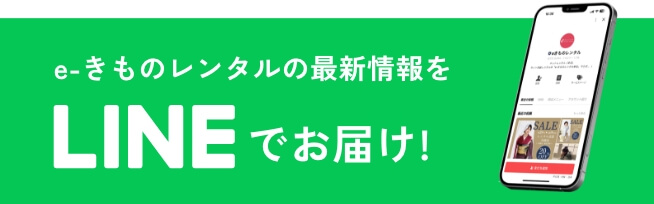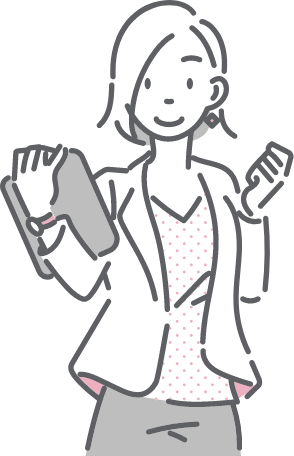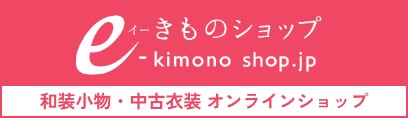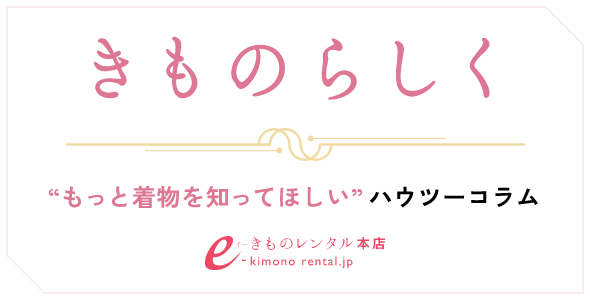
着物のたたみ方を紹介!本だたみや襦袢だたみ・名古屋帯のたたみ方・たたむ際の注意点や保管方法も

着物のたたみ方を紹介!本だたみや襦袢だたみ・名古屋帯のたたみ方・たたむ際の注意点や保管方法も
着物を美しく綺麗に着こなすには、保管の仕方も大切です。とくに着物をきちんとたたんでおけば、シワや型崩れを防ぐことができます。
ただ、一言にたたむといっても着物だけでなく長襦袢や帯も含めると、その方法には色々なパターンがありますよ。
そこで今回は、着物のたたみ方について解説します。着物の正しい保管方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
着物は正しくたたんで保管しよう!
着物を購入したり、親御さんから譲り受けたりした場合は、きちんとたたんで保管しておくことが大事です。
でも着物は、一度広げたらどのように収納したらよいのか分からないという方が、意外と多いのではないでしょうか。確かに着物は洋服と形と構造が違うので、難しく感じるかもしれませんね。
でも大丈夫。一度覚えてしまえばだれでも簡単にたためるようになりますよ。正しくたたんでおくと次に着用する時には、アイロンをかけたりせずにスムーズに準備できるので、とても楽ですよ。この記事を参考にして、ぜひマスターしてくださいね。
着物の主なたたみ方

着物のたたみ方には、主に以下の5つの方法があります。
着物のたたみ方が2通り、あとは長襦袢や帯のたたみ方になります。
本だたみ | 多くの着物で使われる正式なたたみ方 |
袖たたみ | 浴衣や仮絵羽(仮縫い状態)の着物を簡易的にたたむ方法・また一度着物を広げてしまって着るまでに時間がある場合などにも使えます |
襦袢たたみ | 長襦袢をたたむ方法 |
袋帯のたたみ方 | 表生地と裏生地を袋状に縫い合わせた格式の高い袋帯のたたみ方 |
名古屋帯のたたみ方 | 袋帯を短くして一重太鼓結びができるように作られた名古屋帯のたたみ方 |
本だたみの方法
まず手を綺麗に洗いましょう。
できるだけ広いスペースで、衣装敷(いしょうじき)のような着物を汚さないための敷物を敷きます。
その上に、ご自分から見て、衿(肩)が左、裾が右となるように横長に着物を広げましょう。
※着物をたたむ際、シワができたらそのままたたまずに一旦手を止めます。そのつど手の平を使い、アイロンのようにしてシワを伸ばしながらたたんでいきましょう。
- 下前を脇の縫い目で折ります。
- 下前をおくみ線で手前に折り返します
- 上前の衿とおくみを手前に持ってきて、下前にピッタリ合わせます
- 上前の脇縫いを下前の脇縫いに重ねます
- 上半身部分も手前にもってきてピッタリ重ねます(このとき、衿の中心は縫い目に沿って谷折りに、左右の衿はそれぞれの角で山折りにして、各角のところでピッタリ重ね、全体にシワができないように伸ばします)
- 左袖を上前の脇縫いに沿って重ねます
- 裾を肩山まで持ってきて身丈を半分にたたみます(コンパクトにたたみたい場合は、ここで三等分にたたんでもOKですよ)
- 右袖を左右の手でつまむようにして持ち上げ、そのまま身丈に折り重ねたら終了です
袖たたみの方法
- 立ち上がった状態で、着物の内側から背中に向かって(着物と正面から向き合うかたちです)、両袖に左右の腕を通して袖口から出た手の平を合わせます
- 左手で両方の袖口をつまみ、右腕だけ完全に抜きます
- 抜いた右手を着物の外側から回して両袖口をつまみ、左手を抜きます
- そのまま左手で肩山をつまんで胸の前で左右に伸ばします(これで着物が縦長に半分に折れた状態になります)
- 左手で袖の付け根を押さえながら、袖を外側から左に向かって折り重ねます
- 縦に細長くなった着物の裾を床につけて、そのまま屏風のように重ねてたたんだら終了です
※袖たたみは、あくまで簡易的なたたみ方のため、長時間放置するのはおすすめしません。シワや型崩れの原因になるので、収納する際には必ず本だたみをしてくださいね。
襦袢だたみの方法
- まずたたむ前に衿芯を外します
- 衣装敷のような着物を汚さないための敷物を敷いた上に、衿(肩)が左、裾が右にして横長に長襦袢を広げます
- 手前と奥、両方の脇の縫い目に沿ってピッタリと折り、長襦袢を綺麗に整えます
- 衿(うなじ部分)を内側(胸の方向、つまり向かって右方向へ)にたたみ、左右の角をそれぞれ折り目(斜めに入っています)に沿ってもう一度(左に向かって)たたみます
- 下前の脇の縫い目のラインをつまんで身頃の中心に向けてたたみます
- 袖(右手側)も奥へ向かってたたみ、半分でUターンさせて手前でピッタリそろえます
- 上前も同じく脇の縫い目をつまんで身頃の中心に向けてたたみます
- 袖(左手側)もいったん手前にたたみ、半分でUターンさせてピッタリ重ねます(これで横長の長方形になります)
- 裾を肩山まで持ってきて半分にたたんだら終了です
袋帯のたたみ方

袋帯をたたむ際の大事なポイントは、二重太鼓のお太鼓部分にシワが入らないようにすることです。ここにシワが入ると、結んだ際に見た目がとても格好悪くなってしまいますからね。
ここでは、お太鼓部分にシワが入らないたたみ方をご紹介します。
- 衣装敷のような着物を汚さないための敷物を敷いた上に、袋帯をタレ先を左側にして置きます
- 袋帯を右側からたたみ、手先の先端から15cmのラインで外側に折った状態でタレ先の先端に合わせてピッタリ重ねます
- 右の先端を持って左に向かい、半分にたたみます
- さらに半分にたたんだら終了です
普通に右から左、右から左へと3回繰り返してたたんでも良いのですが、それだとお太鼓部分にシワが入る可能性があります。そこで、上記手順の「2」のように手先の先端から15cmのところで折り曲げると、お太鼓部分にシワが入らないので安心ですよ。
名古屋帯のたたみ方
名古屋帯には、「名古屋仕立て」と「松葉仕立て」の2種類がありますが、ここでは名古屋仕立てのたたみ方をご紹介します。
- 衣装敷のような着物を汚さないための敷物を敷いた上に、名古屋帯を裏側を上にし、タレ先を左側にして置きます
- 幅が半分になっているところで上に向かって90度に折ります(このとき右の先端が綺麗な二等辺三角形になっていることを確認してください)
- 続いて左に向かって90度に折ってまっすぐ伸ばしていきます
- タレ先の先端に合わせて手前に向かって90度に折り、さらに右に向かって90度に折ってまっすぐ伸ばします(このとき左の先端が綺麗な二等辺三角形になっていることを確認してください)
- 右先端の二等辺三角形の手前で、余った手先を左に折り返します
- 左右の二等辺三角形を、それぞれ内側に折って、全体が横長の長方形になるようにします
- 真ん中で折りたたんで重ねれば終了です
着物を保管する方法

最後に着物の保管方法について解説しましょう。
そもそも着物はどこに収納するのでしょうか。
昔は、婚礼家具として和ダンスを用意するのが当たり前の時代がありましたが、今ではほぼアンティークですよね。
もちろん、ご自宅に和ダンスがあれば、そこに着物を収納できます。でもそうでない方は、着物用の組み立て式収納ケースがネットで安く販売されているのでお求めください。布製だと通気性も良いためおすすめですよ。
着物や帯は、たたんだ状態で「たとう紙」に一着ずつ入れてから収納します。たとう紙は、着物を購入した時の包み紙ではなく、和紙で作られた収納用のアイテムです。大事な着物を湿気やカビ、虫食いから守ってくれるので、必ず使ってくださいね。
また、たとう紙は表面がツルツルしているため摩擦が少なく、重ねても取り出しやすいメリットもありますよ。大きさは大小さまざまなサイズがあるのでニーズに合ったものをチョイスしてくださいね。
引き出しや収納ケースに着物を収納したら、防虫剤と除湿剤を適量入れて完了です。
あとは少なくとも年に1回は虫干しを行なってください。梅雨が明けた頃がもっともおすすめです。
まとめ

着物や帯は、コツさえ掴めば簡単にたたむことができます。
シワが入らないように手の平でまめに伸ばしながらたたむのがポイントです。帯もお太鼓部分にシワが寄らないように調整しながらたたむようにしましょう。
綺麗に畳めたら必ずたとう紙に入れてから収納してくださいね。虫干しなどのメンテナンスも忘れずに行いましょう。
e-きものレンタルでは、結婚式や入学式、お宮参りや七五三、各種パーティーやお茶会にピッタリの着物を多数取り揃えています。
愛知で創業50年以上の歴史を持ち、トレンドから根強い人気の定番まで幅広いラインナップをご用意しております。着物以外の帯や帯締め、バッグや草履などの小物もセットでお届けする上、クリーニングも不要なため、お着物初心者の方も安心してご利用いただけます。
皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。