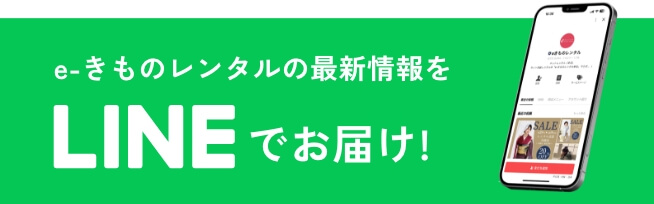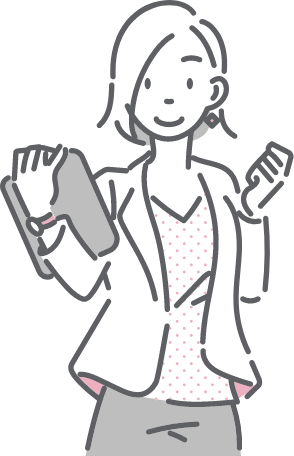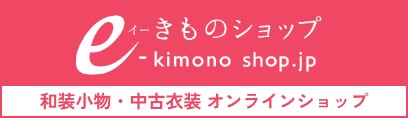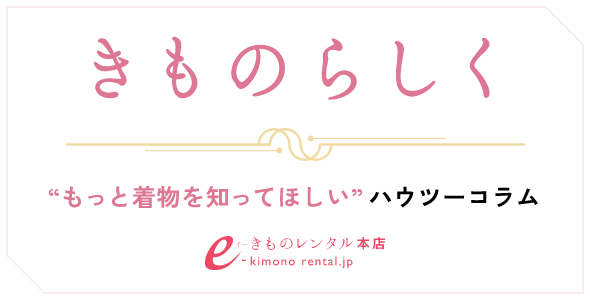
七五三向け着物の小物とは?年齢別アイテムと選び方のコツ

七五三向け着物の小物とは?年齢別アイテムと選び方のコツ
七五三は、お子様の成長を祝う大切な行事。その際にお子様に着せる着物をより華やかに、素敵に見せるには、小物選びも重要です。
ただ、男の子と女の子では準備する小物が異なります。年齢によっても違うので、正しく理解しておく必要があるでしょう。
そこで本記事では、年齢や性別に合わせた小物の選び方や購入とレンタルのメリットについても詳しくご紹介します。これからお子様が七五三を迎える親御様は、この記事を読んでいただければ、七五三準備に慌てなくて済むので、ぜひガイドとしてお役立てください。
七五三とは

七五三は、3歳の男女、5歳の男の子、7歳の女の子の成長をお祝いする行事です。それぞれの年齢で意味合いが異なり、平安時代〜室町時代頃に行われていた、3歳は髪を伸ばし始める「髪置(かみおき)」、5歳ははじめて袴を着る「袴着(はかまぎ)」、7歳は大人と同じ着物を着る「帯解(おびとき)」に由来します。
3歳の「髪置」は、それまで剃っていた髪を伸ばし始める儀式で、子供の健やかな成長を願う意味があります。5歳の「袴着」は、男の子がはじめて袴を着用する儀式で、社会の一員として認められることを表します。7歳の「帯解」は、女の子がそれまで着ていた紐付きの着物から、帯を結ぶ着物に変える儀式で、大人の仲間入りを意味します。
三・五・七というのはいずれも奇数ですが、中国で偶数よりも奇数の方が縁起がいいとされることもあって、男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の年齢(昔は数え年でしたが、今は満年齢が一般的)に神社やお寺にお参りし、健やかな成長を神様にお願いし、ご祈祷を受けます。
七五三のそもそもの起源は、平安時代にまで遡ると言われています。当時は乳幼児の死亡率が高かったため、子供が無事に成長することは決して当たり前ではなく、大変喜ばしいことでした。そこで、子供が成長する節目に、氏神様にお参りして感謝と今後の健康を祈るようになったのです。
江戸時代に入ると、武家社会を中心に七五三の儀式が広まり、一般庶民にも浸透していきました。現在のような形になったのは、明治時代以降のことです。
七五三の流れを確認
七五三が行われるのは、11月15日です。ただし、年によってはこの日が平日だったり、神社やお寺が混雑したりしてお参りできない可能性が高いです。そのため、多くの神社やお寺では早ければ8〜9月頃から七五三のご祈祷を受け付けています。
七五三の基本的な流れは、以下のとおりです。
着付けやヘアメイクを行う
↓
神社やお寺でご祈祷を受ける
↓
写真撮影
↓
食事会
ただし、スケジュールを詰め込みすぎると幼いお子様にとっては負担になるため、食事会や写真撮影は別日程で行うケースも珍しくありません。
七五三の服装は?
七五三の服装は、和装でも洋装でも構いません。
和装にする場合、3歳の男の子は、着物に「被布(ひふ)」というベスト状のアイテムをセットにして着せるのが一般的です。帯は締めず、腰紐や兵児帯(へこおび)で結びます。
▼▼▼おすすめの3歳男の子(被布)の商品はこちら▼▼▼
七五三|3歳男児|被布|対応身長:90~100cm|JAPAN STYLE|#HAOH077
七五三|3歳男児|被布|対応身長:90~100cm|陽気な天使|#HAOH045
七五三|3歳男児|被布|対応身長:90~100cm|#HAOH134
5歳の場合は、羽織に袴姿が人気です。男の子らしく兜や龍、鷹、帆船、松といった柄が大胆に刺繍されたものが定番です。ものによって見た目の印象が大きく違ってくるので、お子さまに似合うことはもちろんですが、本人が気にいるものを選んであげることも大切でしょう。
▼▼▼おすすめの5歳男の子の商品はこちら▼▼▼
七五三|5歳男児|対応身長:110~120cm|HAO5232
七五三|5歳男児|対応身長:110~120cm|E-5-928A
七五三|5歳男児|対応身長:110~120cm|E-5-945A
続いて女の子ですが、3歳の場合は男の子と同じく、着物に被布がオーソドックスなスタイルです。着物は、古典柄とパステルが人気です。
赤やピンクなどの明るく華やかなカラーに、桜や梅、菊といった昔ながらの花や吉祥文様をあしらったものが、古典柄です。はじめての七五三を祝うのにピッタリなコーデといってよいでしょう。
他のお子様と被らないオリジナルな雰囲気を出したい場合は、ピンクやブルー、グリーン、パープルといったパステル調もおすすめです。
いずれにしても、被布は、着物と傾向の異なる色やデザインにすると見映えがしますよ。
▼▼▼おすすめの3歳女の子の商品はこちら▼▼▼
七五三|3歳女児|被布|対応身長:90~100cm|#h-197
七五三|3歳女児|被布|対応身長:90~100cm|式部浪漫|#HAPH668
七五三|3歳女児|被布|対応身長:90~100cm|NATURAL BEAUTY|#E-H-510D
一方、7歳では着物に帯を締めます。
7歳の七五三の起源は「帯解の儀」といわれますが、これは女の子が初めて大人と同じ帯を締める儀式でした。それまでは、帯は窮屈すぎて小さなお子様には負担が大きいため、無理に着せることを避けてきたのです。
7歳向けの着物は、成人式や卒業式で着る振袖に似た見た目(サイズ調整ができる四つ身)で、帯もしっかりと結ぶようになっています。3歳の衣装に比べると、この頃のお嬢様は小学校の入学式も終えてグッと大人びた印象になるので、服装だけでなく写真撮影のポーズも大人っぽさを意識するとよいでしょう。
▼▼▼おすすめの7歳女の子の商品はこちら▼▼▼
七五三|7歳女児|対応身長:110~120cm|式部浪漫|#E-7-166
七五三|7歳女児|着物レンタル|古典柄|対応身長:110~120cm|#E-7-112
七五三|7歳女児|対応身長:115~125cm|JILL STUART|#HAP7358
最近では洋装を選択するご家族も多く、その場合は、男の子は品の良いスーツやタキシード、女の子はキュートなパーティードレスがおすすめです。
親御様の衣装も、お子様と同じく和装(男性は袴、女性は訪問着や付け下げ、色無地(寒い場合は、羽織や道行(みちゆき)などのアウターも)でも洋装(男性はスーツ、女性はワンピースやスーツ(寒い場合は、コートなどのアウターも)でも構いません。ちなみにアウターは、神社やお寺の建物内に入る時には脱ぐのがマナーです。
和装なら小物も準備しよう!

和装というと着物だけを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、七五三の着物コーデでは、着物以外にいくつかの和装小物が必要です。
男児と女児、また年齢によっても異なりますが、肌着代わりの長襦袢、帯とともに使用する帯締めや帯揚げ、髪飾りやバッグ・巾着、草履(雪駄)、懐剣、筥迫(はこせこ・箱せこ)、末広(扇子)などが、その一例です。
詳細は、後ほどお伝えしますが、これらの小物は購入かレンタルで入手することになります。
小物の役割と意味
それぞれの小物には、着物姿をより美しく見せる飾りやアクセサリーの役割だけでなく、魔除けや幸福を願う意味も込められています。
例えば、筥迫(はこせこ)はもともと武家の女性が懐に入れていた化粧道具入れの名残で、美しさの象徴ともいえる存在です。末広(扇子)は末広がりで、将来の発展を願う意味があります。お守りは子供の健康と安全を祈願するものです。
それぞれの小物が持つ意味を理解したうえで、お子様の成長と幸福を願いながら選んであげてください。せっかくですから、お子様にも小物の大切な意味について噛み砕いて説明してあげるとよいのではないでしょうか。
また、小物は写真撮影の際にも重要な役割を果たします。華やかで丁寧に作り込まれた小物は、写真に彩りや可愛らしさ、たくましさを添えるので、お子様の成長ぶりを鮮明に残すことができるでしょう。
女の子に必要な小物
ここからは、女の子と男の子、それぞれに必要な小物をさらに詳しくご紹介しましょう。まずは女の子からです。
3歳
7歳では帯を締めますが、3歳の女の子は帯は使わず、紐で締めてから被布(ひふ)を着せるのが一般的です(絶対的なルールではなく帯を締める方もいます)。
- 被布
- インナーのシャツ
- 長襦袢
- 腰紐(5本くらい)
- 足袋(ストレッチタイプがおすすめ)
- 草履
- 巾着
- 髪飾り(ビラ簪など)
7歳
7歳向けの着物は、振袖に似た見た目でサイズ調整ができる四つ身に帯を結びます。3歳の衣装に比べると、かなり大人びた印象になります。
- 長襦袢
- 半衿
- 肌襦袢
- 帯
- 帯揚げ
- 帯結び
- しごき(帯周りの飾りで、腰から斜め後ろに垂らす)
- 腰紐
- コーリンベルト
- 筥迫
- 髪飾り
- 末広(扇子)
- バッグ・巾着
- 草履
- 足袋(ストレッチタイプがおすすめ)
以下は、あると便利なアイテム。
- 帯板
- 帯枕
- 伊達衿(重ね衿)
男の子に必要な小物
続いて男の子の小物を見ていきましょう。
3歳
3歳の男の子は、女の子と同じく着物に被布を着るスタイルが人気です。
- 被布
- インナーのシャツ
- 長襦袢
- 腰紐(2〜3本くらい)・兵児帯(必要に応じて)
- 足袋(ストレッチタイプがおすすめ)
- 草履(男の子は雪駄が主流)
5歳
男の子は、羽織袴が主流です。
- 長襦袢
- 腰紐(2〜5本くらい)
- 角帯
- 懐剣
- 羽織紐(3本)
- サスペンダー(袴の着崩れを防ぐ)
- 末広(扇子)
- お守り
- 足袋(ストレッチタイプがおすすめ)
- 草履(男の子は雪駄が主流)
【小物選びのポイント その1】帯選び
7歳のお子様が着物を着る際は、帯選びも重要です。
基本的には、着物と同系色で揃えるのがおすすめ。着物が、七五三で最も人気が高いピンクや赤系なら、帯も似た系統の色にすると映えますよ。ブルーやグリーン、イエローなどでも同じことが言えます。正絹の帯が基本ですが、表面が凸凹した縮緬(ちりめん)も幼いお子様にはキュートさが増してよく似合います。
お子様が背が高いとか年齢より大人っぽく見える場合は、黒や濃紺の着物に、思い切ってゴールドで無地の帯を巻いても、とてもオシャレです。金は、赤系統の着物ともよくマッチしますよ。
着物の柄と帯の柄を合わせるのも良いのですが、似た柄があまりにふんだんに使われていると、見た目が騒がしくなり、着物ばかりが悪目立ちする恐れがあります。そのあたりのバランスに注意して選んであげてください。
この年齢の女の子は、好みがはっきりしてくるので、親御様が一方的に決めず、よく意見を聞いて差し上げるとよいでしょう。
【小物選びのポイント その2】帯締め・帯揚げ・しごき選び

帯締めと帯揚げ、しごき(志古貴)は、一見目立たないようでも、そもそも昔ながらのおしゃれアイテムのため、コーデには意外と大きな影響があります。
もっともオーソドックスな選び方は、帯締めも帯揚げもしごきも、着物と同系色で揃えるというものです。同じトーンではなくとも、それぞれで濃淡を付けるとグラデーションのようになって見映えがします。
あるいは、帯締めや帯揚げを単独で、他とまったく異なるカラーにするのもおすすめです。とくに補色(混ざることのない正反対の色)を意識すると、インパクトがあってよいでしょう。
補色の具体例には、以下のようなものがあります。
- 赤と緑
- 青とオレンジ
- 黄色と紺・紫
- 青緑と赤紫
こうした組み合わせを意識すると、他のお子様とは被らず、オリジナリティを強調できるでしょう。ちなみに、落ち着いた印象にしたければ、どんな色にも合う白をもってきてもよいですよ。
また、最近ではエレガントなレース入りの帯揚げも人気です。絞りの帯揚げも、コーデのポイントとして動きをつける意味では、おすすめですよ。
【小物選びのポイント その3】髪飾り選び

七五三用の髪飾りは、以下のタイプがおすすめです。
- つまみ細工
- かんざし
- リボン
- コーム
とくにおすすめは、ちりめんなどの小さな布を折りたたんで作られる繊細な「つまみ細工」です。花や星、動物などがモチーフとなっており、カラーもさまざまで七五三の女の子を可愛く彩るにはうってつけでしょう。
かんざしは、ビラ簪が定番です。歩くたびにひらひら動く見た目に加えて、心地よい音色が響くのが魅力です。
コームは、櫛状のためお子様にとって馴染みがあるうえ、髪の毛を簡単にまとめやすいので、どんなヘアスタイルでも使えます。
【小物選びのポイント その4】草履選び
まず草履のサイズ選びで重要なのは、快適な履き心地と転ばないための安全性を意識することです。七五三の年齢になると、お宮参りの時のようにじっとしていることはありません。
そのため、大きすぎると、歩行中に脱げやすく、転倒の原因になります。といって小さすぎると、足を締め付け、痛みや不快感を引き起こすことがあるでしょう。
サイズは、お子様の足の長さを正確に測り、それに合ったものを選ぶようにします。足の長さは、かかとから一番長い指先までを測り、その長さに1cmほど余裕を持たせたサイズを選ぶのがおすすめです(通常、大人の場合は、足のサイズより小さめの草履を選びますが、お子様の場合はその限りではありません)。
お子様用は一般的に16〜21cmの商品が主流ですが、表示サイズの定義は、ブランドによって異なる場合があります。そのため、必ず試し履きをして、お子様が歩きやすいかどうかを確認してください。その際は、足袋を履いた状態で行いましょう。
さらに、鼻緒は、草履を履く上で、最も重要な部分の一つです。鼻緒が硬すぎたり、細すぎたりすると、足の指の間が痛くなり、長時間履くことができません。とくに、初めて草履を履くお子様には、鼻緒が柔らかく、痛くなりにくい綿やベロア等の素材を選ぶのがおすすめ。
また、とくに3歳のお子様の場合は、草履専用のかかと止めが必須です。かかと止めは、ゴム製のベルトのような形状のものが主流で、鼻緒の左右の付け根にボタンでとめて、かかとにストッパーのように当てて使います。草履に付属されているものもありますが、ない場合は、数百円程度で販売されているので、購入しておくとよいでしょう。
七五三小物に関する注意点
次に七五三の小物に関連する注意点を3つご紹介しましょう。
- 着付けの準備と練習
- 購入かレンタルかを決めよう
- 前撮りのすすめ
着付けの準備と練習
せっかく七五三用の衣装をそろえたとしても、着付けができなければ意味がありません。小物の付け方や使い方も正しく把握しておく必要があるでしょう。
和装は、洋装とは全く仕組みが違うため、手順を理解してその通りお子様に着せる必要があります。とくに七五三用の着物は、浴衣の様に単純ではないので要注意です。
とはいえ、大人の振袖や留袖などと比べるとキッズの着物は、帯のリボンが着脱式になっている「作り帯」を使うなど比較的簡単に着付けできるので、前もってその方法を理解しておけば大丈夫。当日は、順を追って正しく着せるだけです。
着物を購入するショップで尋ねれば、丁寧に教えてくれるでしょうし、着物レンタルの中には、着付けマニュアルなどの案内をくれるお店もありますよ。
当日いきなり着せるのは、時間がかかったり、衿の重ね方や帯の締め具合が上手くいかなかったりする可能性があるので、おすすめしません。必ず前日までに練習をしておき、綺麗に着付けるコツを押さえ、どれくらい時間がかかるか把握しておきましょう。
お子様にも「着物ってこんな感じなんだ」という感覚を味わってもらっておくと当日に戸惑うこともありませんよ。
購入かレンタルかを決めよう
上記のように、七五三用の着物は、知人から借りるとか、お兄様やお姉様が使ったものがない限り、基本的には購入するかレンタルのいずれかになるでしょう。また、どちらにするかをできるだけ早く決める必要があります。
というのも、七五三直前では、購入でもレンタルでも、小物を含めた商品の在庫が少なくなる可能性が高いからです。せっかくなら親御様もお子様もお気に入りの素敵な着物を着せてあげたいですよね。
購入とレンタルそれぞれのメリットについては、後ほど詳しくお伝えするので、それを参考にして決めてくださいね。
前撮りのすすめ

七五三当日のスケジュールは、長距離を移動したり、神社やお寺でご祈祷を受けたり、食事をしたりと意外にハードです。それに加えて七五三では欠かせない写真撮影もとなると、とくに3歳や5歳のお子様には負担が大きくなるでしょう。
そこでおすすめするのが、前撮り(スケジュール的に無理なら「後撮り」でもOK)です。七五三より前倒し(後撮りは後ろ倒し)で、写真スタジオで家族も含めた写真を撮影したり、屋外でロケーション撮影を行ったりするのです。すると、時間や気持ちに余裕がうまれ、お子様の疲れも少ないため、素敵な表情の写真が撮れる可能性が高まるでしょう。
前撮りと七五三本番の2回着付けをするとなると親御様は少し大変かもしれませんが、一生の思い出ですから、ぜひ検討してみてください。
小物を購入するメリット
それでは、ここから七五三小物を購入するメリットについて解説しましょう。
実際のところ、七五三で小物だけを購入するケースは稀です。基本は、着物がメインで、それにともなって小物もフルセットで購入する形になります。
そのメリットは、以下の通りです。
- 好きなデザインの着物をジャストサイズで着られ、お気に入りの小物が選べる
- 他人が着た着物や使った小物を使わなくて済む
- 品質にこだわらなければ意外と安い商品もある
- 七五三の記念品として保管できる
- 弟や妹ができた場合は、使い回せる
小物をレンタルするメリット
着物レンタルで着物を借りると、一般的には、以下※の一覧のような和装小物一式を無料でレンタルできます。
※長襦袢、腰紐、結び帯、帯締め、帯揚げ、帯枕、伊達じめ、草履、バッグ、箱せこ、しごき、角帯、懐剣、羽織紐、末広(扇子)、お守り、足袋など
レンタルを利用すると、着物を単品で購入するより安い(とくに純粋な日本製は高額になります)だけでなく、小物もセットとなるため、トータルのコスパがかなりよくなります。
ちなみに着物レンタルには、他にも以下のようなメリットがあります。
- 豊富な商品の中から自由に選択できる
- ネットレンタルなら、自宅や出先などどこでも、いつでもページを検索して予約・注文できる
- 人気のブランドや新着の着物が着られる
- お子様だけでなく、他の家族の着物やスーツ、ワンピースなども安くレンタルできる(lineの公式アカウントから登録するとクーポンがもらえてお得といったサービスや・期間限定のキャンペーンなどが多い)
- オフシーズンならさらに格安でレンタルできるケースもある
- ネットレンタルの場合はスマホがあれば、登録から予約、返却まで簡単に行える
- 商品を自宅に郵送で届けてもらえる(送料無料のサービスも多い)
- お支払いは、クレジットカード・代金引換・銀行振込・コンビニ・ATMに対応(ショップによる)
- 返却時も連絡をせずに送り返すだけ
- 急なニーズでも対応できる(ネットレンタルなら24時間・365日いつでも注文可能)
- 返却時のクリーニングも不要なため気軽に利用できる
- 収納を考えなくて良い
以上のように利点が多い反面、とくにネットレンタルの場合は、リアル店舗と違って試着ができないため不安という声がよく聞かれます。しかし、最近のネットレンタルでは専用サイトの商品ページで、鮮明な複数の画像とともにサイズについても細かな情報が表示されています。
その内容を確認して注文すれば、届いてからデザインが思った通りでないとか、サイズが合わないといったトラブルはほぼありませんので安心してください。
ママの小物はいらないの?

お母様が和装の場合は、訪問着や付け下げ、色無地などが一般的です。着付けの際は、お子様と同様というよりそれ以上にさまざまな種類の小物を用意する必要があります。
基本的には、以下の通りです。
- 長襦袢
- 袋帯
- 帯揚げ
- 帯締め
- 重ね衿
- 肌襦袢
- 腰紐(4本)
- 伊逹締め
- 帯板
- 帯枕
- 衿芯
- 和装ベルト
- 草履・バッグセット
- 足袋
お父様も袴を着る場合は、以下のような小物が必要です。
- 長襦袢
- 腰ひも
- 帯(角帯)
- 羽織ひも
- 補正用のタオル
- 足袋
- 雪駄
小物以外にあると便利なアイテム!
七五三当日は、和装小物以外にも持参しておくと役に立つアイテムがいくつかあります。
- 着替え(お子様が疲れた際に着替えられる普段着)
- 履き慣れた靴と靴下(お子様が疲れた時に履き替える)
- 長靴・レインコート(雨対策)
- 小さめの毛布やマフラー・カイロ(防寒対策)
- 大きめのタオル(食事や水分補給の際に汚れ防止のために使う)
- 洗濯バサミや着物クリップ2〜3個(トイレや雨天の際に裾や袖が濡れないように)
- 酔い止めの薬(長時間電車や車に乗る場合)
- ウェットティッシュ
- 上記のアイテムが収納できる大きめのバッグ
トイレ対策も忘れずに!
七五三に着物でお参りする際に、誰もが困るのがトイレです。小さなお子様は、トイレの回数が多く、しかも急に「行きたい!」と言い出すものですよね。そこで、簡単にトイレができるように、あらかじめ手順をマスターしておくことをおすすめします。
基本は、大きめの洗濯バサミか着物クリップを2〜3個持参し、すぐに取り出せるようにしておきます。用を足す際に、襦袢と着物の裾をぞれぞれ持ち上げて袖や上半身の適当なところで留めます。
無理にあげすぎると着崩れを起こす恐れがあるので、ゆっくり丁寧に行ってください。終わったら、襦袢→着物の順で下ろし、元の状態に整えます。
男の子で袴を履かせる場合は、脱がなくても裾を上げるだけで済むスカート型の「行燈(あんどん)袴」(脱がなければならない「馬乗り袴」ではなく)がおすすめです。
3歳のお子様は間に合わない可能性があるので、おむつを履かせておくと安心ですよ。
7歳のお子様は、あらかじめ手順を教え、洗濯バサミなどを持たせてあげれば、親御様が付き添わなくても大丈夫でしょう。
まとめ:七五三の小物選びを楽しもう

七五三の着物コーデでは、小物選びもとても重要です。女の子なら髪飾りや巾着、箱せこ、草履など、男の子の場合は、懐剣やお守り、雪駄などをどのようなタイプにするかで、全体のイメージが大きく変わってきます。お子様と一緒に楽しみながら、ピッタリの小物を見つけて、最高の思い出を作りましょう。
お子様の好みや個性を尊重しながら、ぴったりの小物を見つけてあげてください。そして、七五三当日には、素敵な着物姿で、最高の思い出を作ってあげてください。
e-きものレンタルでは、七五三用の衣装を多数取り揃えております。女の子向け着物は3歳用と7歳用、男の子向けの羽織袴、またドレスやスーツ、タキシードなど洋装についても各種ご用意しております。
着物だけでなく、髪飾りや被布、襦袢、腰ひも、巾着、草履、箱せこ、角帯、懐剣、羽織紐、末広(扇子)、お守りといった着付けに必要な小物も、お客様に代わってベテランスタッフがコーディネートのうえセットでお送りいたします。送料は日本全国無料(一部地域を除く)、ご返却の際はクリーニングも不要です。
お父様向けの男性スーツとお母様用の着物やスーツ、ドレス、ご姉妹やご兄弟の衣装も割安でレンタルできる家族割引クーポンもありますので、ぜひご利用ください。