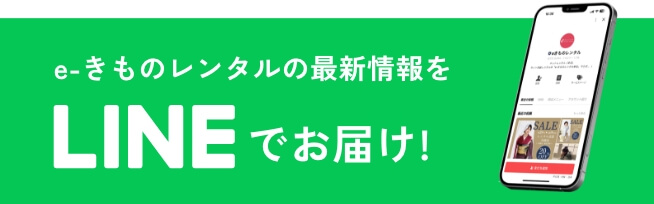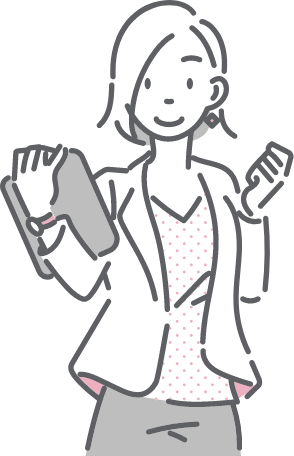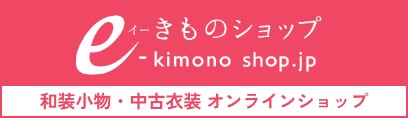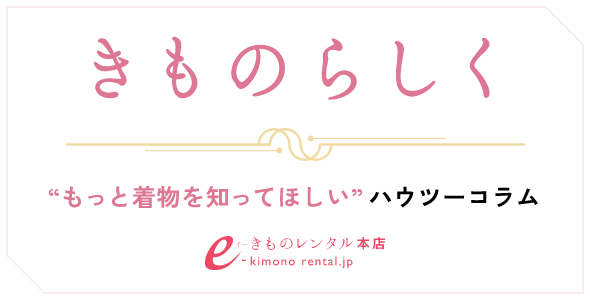
神前結婚式とは?仏前結婚式との違いや流れ・費用・衣装・髪型まで基礎知識を徹底解説!

神前結婚式とは?仏前結婚式との違いや流れ・費用・衣装・髪型まで基礎知識を徹底解説!
結婚式のスタイルには、神前式やチャペル式、仏前式、人前式など、さまざまなものがあります。どのスタイルにするかで挙式の場所も流れも大きく違ってくるので、基礎的な知識を持っておくことは、とても大事でしょう。
そこで今回は、神前結婚式について特集します。
神前結婚式の起源や詳しい流れ、神社の決め方、費用や衣装について詳しく解説します。すでにご結婚が決まっていてこれから式場探しをする方や、結婚はまだだけど今後のために知っておきたいという方も、ぜひ参考にしてくださいね!
神前結婚式とは?

神前結婚式とは、神社でとり行う神道(しんどう)式の結婚式を指します。
私たちが生きている日本では、古来より「八百万(やおよろず)の神」という、この世の万物に神が宿るとの考え方がありました。この思想や信仰にしたがってさまざまな神様をお祭りしてきたのが、「神道」です。
神道には特定の偶像がなく、神は常に自分たちの周りに存在するため、心さえあればわざわざ形式立てて祀ったり祈ったりする必要もないという考えがあったといいます。
しかしやがて同じものを信仰する人たちが集まり、祭りを行う場所を作って拠り所とする発想が生まれて神社が各地に作られるようになりました。
神道の考え方に基づいて、お正月や節分、七五三といった身近な行事があるにもかかわらず、多くの日本人は「神道」の意味をあまり深く知らなかったり、自分がその信仰者であるという認識が薄かったりします。ここが、キリスト教やイスラム教を日常的に信仰する海外の人たちとの大きな違いであり、不思議に思われる点でもあります。
国によっては初めての挨拶のときに「あなたの宗教は?」と尋ねるのが当たり前というケースもあります。きっとこう聞かれると、ほとんどの日本人は戸惑ってしまうでしょうし、上手く説明できないのではないでしょうか。
ところで今日(こんにち)では、結婚式も神社で行うのが常識となりましたが、これは意外と最近になってからのことで、もとはそうではありませんでした。
神前結婚式の起源
日本の結婚式は、もともと「祝言(しゅうげん)」という名で、家庭の床の間や神棚の前で行われていました。新婦は、新郎の家に文字通り直接「嫁入り」したわけです。
それが明治33年、大正天皇が初めて日比谷大神宮(現在の東京大神宮(東京都千代田区))で挙式されたのがきっかけとなって神前結婚式が世の中に広まりました。そのため歴史はまだ100年と少しくらいで、意外と浅いのです。しかも今のような形が整ったのは、昭和に入ってからです。
神前式では、祝詞奏上や三三九度(三献(さんこん)の儀)、玉串拝礼(たまぐし拝礼)などの儀式が行われ、神様の前で結婚を誓います。
仏前式との違いは?
仏前式は、寺院において仏様の前で結婚を誓います。仏前式での挙式は、全カップルのうち1〜2%といわれるため、ほとんど馴染みがないかもしれませんね。
先祖代々お世話になってきた菩提寺があれば迷いはないかもしれませんが、両家が同じ宗派とも限りませんよね。実は、寺院側は宗派が違っても受け入れてくれるところが多いです。
日本独特の事情ですが、神社と寺院はまったくの別物ではなく、ともにさまざまな関係を持ちながら発展してきた歴史があります。最古の神社は3世紀に創建された島根県の出雲大社で、寺院が増え始めたのは7世紀頃と神社の方が早いです。ただ、神道も仏教もそれぞれに相手を否定せず共存共栄の関係を築いてきたので、全国の神社仏閣を巡ると、神社のようなお寺や、寺院のような神社が数多く点在しますよ。
例えば、豊川稲荷という大変有名な寺院が愛知県にあります。ここはお寺ですが、「稲荷」ですから「キツネ」を祀っています。豊川稲荷に並ぶ三大稲荷で人気の京都・伏見稲荷は、「神社」です。面白いですよね。「こっちがお寺なんだから、そっちもお寺にしなよ!」と喧嘩することはないのです。
ただ、明治になって国家神道という形で神道を国の宗教とした時代(第二次世界大戦後に現在の憲法が施行されるまで)があり、その際に「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」といって多くの寺院や御身体である仏像などが破壊・焼却されました。中には国宝級の貴重な仏像などもあったので、とても勿体無い残念な出来事でした。
この影響で国民の間では、お寺は亡くなった後にお世話になったり、先祖を供養したりするところで、神社の方がどちらかといえばおめでたい場所としてすみ分けされ、とくに結婚式ではクローズアップされることが増えたといえるでしょう。
神前結婚式は誰でもできるの?

さて、そんな神社での神前結婚式ですが、誰でも挙式できるのでしょうか?
答えは「Yes」です。氏子やその家族でなければダメ、などというかたいルールはありません。信仰の有無や宗派に関係なく、誰でも希望すれば神前結婚式はできますよ。
どれくらいのカップルが神前結婚式を挙げるの?
正式な統計があるわけではありませんが、神前結婚式を挙げるカップルは全体の2割弱程度のようです。もっとも多いのが、チャペル式で、キリスト教にのっとって教会で行うものです。
どこの神社がいいの?
神社は、宗教法人として認められているだけでも全国に8万社以上あります。そのため、どこで式を挙げれば良いのか迷ってしまうかもしれませんね。
結論から言うと好きな神社で構いません。地元で代々お世話になっているとか、ご利益があるらしいということで心が惹かれるとか、両家の実家から近くて縁結びとして人気など・・・。神職や巫女さんがいて挙式するスペースがあって、結婚式を受け入れてくれるところであればどこでも可能ですよ。
実は、神前結婚式だから神社で行うとも限りません。その割合は約半分くらいといわれます。残りは、ホテルや結婚式場内にある神殿で済ませるケースが多いです。
どんな日がいいの?

いつ神前結婚式を行うかは、そのカップルの自由です。
ただ昔から縁起がいいとされるのは、「大安」か「友引」「先勝」などです。大安と友引は、六曜(ろくよう)の考え方でどちらも1日中「吉」とされる日で、先勝は午前中なら「吉」とされます。
「仏滅」や「赤口」は、凶日のため避けた方がよいでしょう。
神前結婚式には誰が参列できるの?
神前結婚式には、希望者なら誰でも参列できますよ。身内かそうでないかは関係ありません。
ただし、神社によって式場スペースはまちまちです。どれくらいの人数が入れるかを事前によく調べて参列者を決めるのがよいでしょう。
神前結婚式の流れ
続いては、神前結婚式の流れと、挙式後の流れについて解説しましょう。
挙式の流れ
細かく見ると神社によって挙式の流れは違いますが、オーソドックス(やや丁寧め)な流れをご紹介しましょう。以下の15の手順になります。
1 | 参進の儀(さんしんのぎ) | 神職や巫女に導かれて、新郎新婦、両家の親、親族の順に境内をゆっくりと歩いて神殿に向かいます。ここで雅楽が流れることもありますよ。 |
2 | 着座 | 神殿に入ると、神様に向かって着席します。新婦が神様に向かって左、新郎が右に座ります。 |
3 | 修祓(しゅばつ) | 神職によって祓詞(はらえことば)が奏上されて新郎新婦とその他の参列者をお祓いします。 |
4 | 斎主一拝(さいしゅいっぱい) | 斎主(式をもっとも中心で司る神職)をはじめ全員が起立して拝礼します。 |
5 | 献饌(けんせん) | 神前に神饌を供えます。神饌とは神様にお供えする食事で、お米、お神酒、水、塩、山の幸や海の幸などです。 |
6 | 祝詞奏上(のりとそうじょう) | 神様に永遠の愛を誓う証として、斎主が祝詞を奏上します。 |
7 | 三献の儀(さんこんのぎ) | いわゆる「三三九度(さんさんくど)」のことで、大中小の盃にお神酒を注いで酌み交わし、夫婦の契りを結びます。「小」は先祖や親に今までの過去を感謝し、「中」は結婚相手と出会えた現在への感謝、「大」はこれから幸せな家庭を築くと言う未来への願いを意味します。 |
8 | 誓詞奏上(せいしそうじょう) | 新郎と新婦が、神前で愛を誓います。「結婚の報告と感謝」「2人で幸せな家庭を築いていくという誓い」「神様にいつまでも見守ってもらうことをお願いする締めの言葉」という3つの柱からなります。 |
9 | 神楽奉奏(かぐらほうそう) | 巫女が神様に感謝の舞を舞う儀式です。神楽を奉納することによって一層の恵みが与えられるとされます。 |
10 | 玉串拝礼(たまぐしはいれい) | 神様への敬意を表すために榊の枝に紙垂(しで)などをつけたものを神前に奉納します。2人揃って二礼二拍手一礼を行います。 |
11 | 指輪交換 | 互いの左薬指に指輪をはめます。ちなみに指輪交換は西洋の儀式のため、絶対に行わなければならないわけではありません。腕時計やネクタイピン、ネックレスなどにするカップルもいますし、このプロセスをスキップして何もしないケースもありますよ。 |
12 | 親族盃の儀(しんぞくさかずきのぎ) | 両家の親族全員で盃のお神酒をいただき、結婚の儀は終了となります。 |
13 | 撤饌(てっせん) | 神に捧げた神饌をお下げします。 |
14 | 斎主一拝(さいしゅいっぱい) | 神様に向かって斎主の動きに揃えながら全員で起立のうえ拝礼します。 |
15 | 退場 | 神殿から退場します。 |
挙式後の流れ
挙式後は、披露宴に移るのが一般的な流れになります。神社の施設内に披露宴会場がある場合は、そのままお色直しをするなどして披露宴をとり行います。
神社に披露宴用のスペースやサービスがない場合や、特別に思い入れがある場合は、ホテルや披露宴会場、お気に入りのレストランなどを別に確保して行うパターンも多いですよ。
ただ移動の場合は、バスやタクシーをチャーターするなど手間とお金がかかるので、その点は注意が必要です。
神前結婚式の費用は?
神前結婚式の費用は、とくにいくらとは決まっていません。利用する神社やサービスによって違います。
神社での挙式のみなら初穂料として5〜10万円くらいが相場です。ただ、これがホテルや結婚式場となると30万円以上はかかると考えておいた方がよいでしょう。
さらに着付けやヘアセット、メイク、衣装、披露宴も込みになると、数十万円〜200万円前後かそれ以上は必要になるでしょう。
神前結婚式の衣装は?

神前結婚式だからといって、絶対に着用しなければならない衣装はありません。和装でも洋装でも好みで選択できますよ。
ただ、とくに神前結婚式の場合は、新婦は「白無垢」で新郎は「紋付袴」というのが昔ながらの定番です。
新婦の衣装
白無垢は、室町時代から始まったとされる日本の伝統的な婚礼衣装です。全身を白で統一することで、純潔や無垢を象徴し、「嫁ぎ先の色に染まる」という意味も込められています。着物の格式では最高の第一礼装に属し、まさに神聖な儀式にふさわしく、この上なく気品に満ちた衣装ですよ。
後ほど詳しくご紹介しますが、白無垢の際、正式には文金高島田(ぶんきんたかしまだ)に角隠し、または綿帽子をかぶります。また、他の着物にはない裾の長さであえて床にするように仕立てられているのが大きな特徴です。
普段ではありえない大きくて重みのある髪型に、裾の長さゆえゆったりと歩を進める姿は、花嫁さんの気品と美しさをより一層引き立てます。その様子に参列者からはため息が漏れ、と同時にその目線を釘付けにすること間違いなしです。
一生のうちでこのような経験は滅多とないので、新たな人生の門出を祝うに相応しい最高の花嫁コーデといえるでしょう。
| 結婚式の白無垢はレンタルで!色打掛や引き振袖との違い・着付けなど花嫁の疑問を解決! 神前結婚式の定番である白無垢について詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 |
和装の婚礼衣装には、白無垢の他に「色打掛」や「引き振袖」もあります。
色打掛は、白無垢の一番外に着る白打掛の代わりに華やかで美しくカラフルな打掛を着用します。挙式中に着る方もおられますが、挙式は白無垢にして、披露宴やお色直しで色打掛に着替えるというのが一般的です。元々は白無垢の方が格上でしたが、現代では同等に扱われるようになりました。
引き振袖は、成人式の振袖と違っておはしょりを作らず、裾を長くして引きずるように着るのが特徴です。格式としては、白無垢や色打掛と同様で、最高ランクになります。
成人式で着用される振袖は、一般的に中振袖といって袖が95cm前後です。
それに対して、引き振袖は、大振袖になり、振袖の長さが115cm以上もあります。裾には「ふき綿」が入っており、裾のラインが美しく豪華に見える工夫がされています。
新郎の衣装
白無垢に合わせる新郎の衣装は、黒紋付羽織袴(=紋付袴)が一般的です。もっとも格式の高い正装であり、白無垢とのバランスもバッチリですよ。購入の場合、家紋は自身の家のものになりますが、レンタルの場合には「通紋(つうもん)」といって家柄に関係なくどなたでも使用できる家紋が使われています。
近年では、新郎も個性を表現したいというニーズが高まり、紺やグレーといった色物の袴や羽織を選ぶ人も増えています。また、柄物の羽織もあり、かなり斬新ですが、華やかで個性的な雰囲気を演出できますよ。
白無垢でもっとも外側に着る白打掛のすぐ下の掛下(かけした)も基本は白のところ、最近ではそれ以外のカラーや柄の入ったタイプ(色掛下という)をチョイスする方が増えており、その場合は、新郎も色物や柄物の紋付袴をペアで着用するケースがあります。
白無垢・色打掛・引き振袖・紋付袴なら着物レンタルがおすすめ
おそらくほとんどの方にとって、神前式で用いられる白無垢や色掛下、引き振袖、紋付袴は、結婚式が終わったら二度と使うことはないでしょう。
そのため、結婚式のためだけにわざわざ購入するのは、かなり勿体無いかもしれません。それより着物レンタルを利用した方が、圧倒的にコスパが良いのでおすすめです。
人気や実績のあるショップなら、トレンドも意識した素敵なデザインのものが多数揃っているので、ご自分に合ったお気に入りが見つかる可能性が高いですよ。
しかも、白無垢や色打掛、引き振袖は、メインの着物だけでなく、着付けるために多くの小物(長襦袢、腰紐、掛下、草履、末広など)が必要です。着物レンタルなら、そうした小物もセットで貸してもらえるので、かなりお得でしょう。購入の場合は、もちろんそうした小物を全部買い揃えなければなりませんからね。
他にも、以下のようなメリットがあります。
- 着物一式が郵送で届き、郵送で返却できるのでとてもラク
- クリーニングが不要
- 保管スペースが不要
- 虫干しなどのメンテナンスが不要
結婚式に向けて、またその後の新婚生活も何かとお金がかかりますよね。着物レンタルで安く借りることができれば、浮いたお金を他の予算に回せるのでおすすめです。
神前結婚式のヘアスタイル

ところで白無垢にはどのような髪型が似合うのでしょうか?白無垢の歴史は、室町時代にまで遡りますから伝統にしたがうなら髪型は日本髪になります。具体的には、「文金高島田」が基本です。
文金高島田は、江戸時代に未婚女性の中で流行した「島田髷(まげ)」の一種で、現在の形になったのは明治時代以降といわれています。
島田髷には、奴島田、投げ島田、つぶし島田、芸者島田など、さまざまな種類がありますが、中でも文金高島田は、髷の根を高い位置で結んだ最も格が高いとされるスタイルですよ。
文金高島田は、トップの「髷」、「前髪」、両サイドの「鬢(びん)」、髷を折り曲げた後頭部の「いち」、うなじ部分でまとめた「たぼ」の5つのパーツからなります。
文金高島田では、角隠しを付けるか、綿帽子をかぶります。特にどちらでなければいけないという決まりはなく、好きな方を選んで構いませんよ。ただし、角隠しは、色打掛や引き振袖に合わせても良いのですが、綿帽子は白無垢オンリーなので注意が必要です。
また、綿帽子は、もともとはホコリ避けや防寒の目的で利用されていたアイテムのため、昔は神社や披露宴会場の屋内でかぶるのはルールに反していました。でも最近では、そこまでこだわることはなくなっているため、気にしなくても大丈夫ですよ。
角隠しは帯状の真っ白な布で、前髪を隠すように鉢巻の要領で巻いて後ろで留めます。
綿帽子は、文金高島田の上からかぶるか、最近では洋髪でも頭頂部に綿帽子キーパーという専用器具を乗せて、その上からかぶる人たちが多くなっています。
ただ、最近では日本髪のルールもかなり緩くなり、むしろ角隠しや綿帽子を被らず洋髪のまま行うケースも増えつつあります。この場合は、水引やリボンといった髪飾りでアレンジしたり、金箔やラメでさらに明るく華やかに演出したりできるので、かなりオシャレでインパクトもありますよ。洋髪の方が楽ですし、お色直しでのアレンジもしやすいですから、トータルで考えるとその方がよいのかもしれませんね。
 | 白無垢のおしゃれな髪型は和髪?洋髪?伝統とトレンドのスタイル・花嫁の今どきヘアアレンジを紹介! 白無垢に合うおしゃれな髪型詳しく解説しています。髪飾りを使ったアレンジも紹介!合わせてご覧ください。 |
まとめ

神前結婚式は、伝統文化にそったもっとも日本らしい結婚式のスタイルといえます。
とくに神社で挙式する場合は、お祀りする神様のこと、その神社の成り立ちや歴史などについて詳しく知ると、より神聖な気持ちになると同時に、結婚できる幸せを強く実感できるのではないでしょうか。
新婦は白無垢に、新郎は紋付袴に身を包み、厳かな雰囲気の中で永遠の愛を誓い合う神前結婚式は、一生の素晴らしい思い出になるはずです。
e-きものレンタルでは、結婚式向けに、白無垢や色打掛、新郎向けの紋付袴、お母様やご親族の黒留袖・色留袖・訪問着などを幅広く取り揃えております。
愛知で創業50年以上、経験豊富なベテランスタッフが大切な婚礼準備を心を込めてサポートいたします。小物も無料でコーディネートしてお送りしますので、着物レンタルが初めての方もご安心ください。
皆様のご利用を心よりお待ち申し上げております。